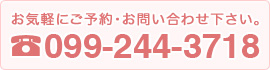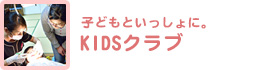お知らせ・小田原歯科便り
- HOME
- > お知らせ・小田原歯科便り
- > スタッフブログ
スタッフブログ
インフルエンザ対策
2017年01月13日
こんにちは
小児の虫歯予防・成人の歯周病予防に努めている、鹿児島市小田原歯科、歯科衛生士の川井田です
寒い日が続きインフルエンザのニュースもよくききますね
今回は風邪・インフルエンザ予防についてお話したいと思います。。。
1、手洗いうがい
私たちは毎日、様々なものに触れていますが、それらにふれることにより、自分の手にもウイルスの体内進入を防ぐため手洗いうがいをこまめにしましょう。
2、健康管理
インフルエンザは免疫力が弱っていると、感染しやすくなりますし、感染したときに症状が重くなってしまうおそれがあります。普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ免疫力をたかめておきましょう。
3、適度な湿度を保つ
空気が乾燥すると、喉の粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。
4、人混みや繁華街への外出を控える
インフルエンザが流行してきたら、不要不急の時はなるべく、人混みや繁華街への外出を控えましょう。
キケン!!冬の熱中症
2017年01月10日
こんにちは
小児のむし歯予防、成人の歯周病予防につとめている鹿児島市の小田原歯科 歯科助手の井手之上です
寒さも増して、お風呂にゆっくり浸かって温まる方も多いのではないでしょうか
ですが、お風呂で熱中症になるのをご存知ですか!??
ということで!!本日は冬の熱中症についてお話いたします
冬に熱中症になることがあるのでしょうか・・・?
ご存知のとおり、冬は乾燥する季節です この乾燥によって、身体から自覚がないまま水分が奪われてしまい、脱水の一歩手前の状態になりがちです。
この乾燥によって、身体から自覚がないまま水分が奪われてしまい、脱水の一歩手前の状態になりがちです。
夏場は意識して水分補給をこまめにしますが、冬はそこまで気にしなくなってしまい、気づかないまま放置していると大変なことになってしまいます
誰でも冬の熱中症になる可能性はありますが、
特に、子どもたちやご高齢の方は注意が必要です
子どもたちは身体が未発達なため、脱水になりやすく、
ご高齢の方は喉の渇きを感じにくくなったり、食事の量が減ってしまうことが原因と言われています。
次に、熱中症になりやすい場所はどこでしょうか??
室内、お風呂、車の中・・・・実は、どこも熱中症になる危険があるのです!
①室内
部屋のなかは換気をしない限りは外からの自然な空気が入ってこないため、乾燥してしまいます。
また、ストーブなど暖房器具を使うとさらに部屋の中の空気は乾燥してしまいます
②お風呂
ちょっと意外かもしれませんが、とっても注意が必要になります
「寒い!!」と、熱いお風呂に肩まで浸かってついつい長湯をしてしまう・・・なんてことありませんか??
脱衣所とお風呂の気温差で血圧が激しく変動して失神や心筋梗塞などを引きおこしてしまう可能性も考えられます。
③車の中
車の中はフロントガラスやサイドガラスから直射日光を浴びやすいので、体温が上がりやすいといわれています。
加えて、運転中は水分補給がしにくいので、脱水状態になりやすくなってしまいます。
冬でもこまめな水分補給をしっかり行い、1日中部屋にこもらずに暖かな時間に外へ出て散歩などで身体を動かすと
皮膚の発汗機能が動き出して代謝がよくなって体の余分な熱を外に出してくれるようです!


まだまだ寒い季節は続きますが、冬の熱中症に気をつけてお過ごしくださいませ~~
年末年始のお知らせ
2016年12月28日
こんにちは、小児の虫歯予防・成人の歯周病予防に努めている、鹿児島市小田原歯科の副院長前田です。
あっという間に年の瀬ですね。ということで、本日は年末年始の休診日のお知らせをいたします。
12月29日の午後1時より1月3日まで、誠に勝手ながら休診とさせていただきます。
なお、1月4日からは通常通りの診療となります。
休診期間中は何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
かぼちゃと冬至
2016年12月21日
こんにちは。鹿児島県鹿児島市で成人の歯周病予防と小児のむし歯予防に
力を入れている小田原歯科の歯科衛生士宇治野です
本日12月21日は冬至ですね!
冬至とは北半球で一年のうちで太陽の位置が最も低くなる日のことで、
日の出から日の入りまでの日照時間が一年でもっとも短い日のことです
なんと日照時間の一番長い夏至の日と比べると、北海道で6時間半
東京では4時間40分も差があるのです。
・・・と言うことは鹿児島は3時間くらいの差でしょうか?
日本でもこれだけの違いがあるなんて改めて驚きです!
ところで冬至と言えば、かぼちゃやゆず湯
でもどうして夏のお野菜のかぼちゃを真冬に食べるのでしょう??
かぼちゃは漢字で書くと「南瓜」 なんきんと読みます。
もともと冬至には「ん」の付くものを食べると「運」が呼び込めると言われていて、
にんじん、だいこん、れんこん、うどん、ぎんなん、きんかん・・・など「ん」のつくものを
「運盛」と言って縁起を担いでいたそうです
栄養たっぷり、「運」だけでなく「栄養」も付く食品ばかりですね
かぼちゃにはビタミンAやカロチンが豊富に含まれ風邪や脳血管疾患に効果的なのです。
みなさんも「ん」のつく食べ物で「運」と「栄養」をたっぷり摂って
さむ~~~~い冬に備えましょう
なにかと忙しい冬。。冬バテにご用心です!!
2016年12月09日
こんにちは
小児のむし歯予防、成人の歯周病予防に努めている鹿児島市小田原歯科の歯科助手井手之上です
すっかり寒くなり、みなさま風邪をひいたり体調をくずしてしまっていませんか??
私は歩いて通勤をしており、通勤時にはマフラーとコートが必須アイテムになっております
さて、今日は冬バテについてお話いたします
夏バテはよく聴く言葉ですが、冬バテとは・・・???
まずは、夏バテとの違いについて
夏バテ・・・・・室内と外との温度差で自律神経がへとへとになってしまい、心身ともにふんばりがきかなくなってしまうこと
冬バテ・・・・・寒さや年末年始の忙しさから身も心も緊張状態が続いて休まらず、疲れやすいうえに寒さによって体内で熱が十分作られずに筋肉が衰えがちになって元気も不足してしまい、イライラやだるさが抜けず、風邪を引きやすくなってしまうこといいます
年末年始はクリスマスや忘年会、お正月に新年会・・・とイベントが続いて飲食の機会も多く内臓にも負担を大きくかけてしまい、
リラックスモードの副交感神経が働く機会が減りがちになってしまいます
また、寒さで体が冷えることで血管が収縮して血流が悪くなることも冬バテの原因のひとつでもあります
では、冬バテから脱却すべく4つのポイントをご紹介します

①体を温める
39℃前後のお風呂にゆっくりつかると、体がじんわりあたたまりリラックスモードの副交感神経が働きやすくなります
②急に体を冷やさない
急に体が冷えると、交感神経が一気に緊張状態になってしまいます
「ちょっとそこまで・・・」のおでかけのときでも、防寒アイテムをお供に・・・
③室内でできる運動
室内でゆっくりとしたペースでできる運動を続けると、副交感神経が動きやすくなります
④規則正しい食事を
基本は一日3食バランスよく・・が大切なのですが、
☆自律神経を整える成分が入っている玄米
☆ストレスが増えてしまうと交感神経ばかり働いて体の中の活性酸素を増やすので、抗酸化作用のあるきのこ類・ゴマ・緑黄色野菜、海 藻類など
をしっかりと摂ることがポイントになってきます
今年の冬は、どうぞ冬バテに気をつけてお過ごしください~~